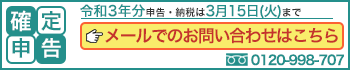青色申告を選択することによって、さまざまなメリットを受けることができます。今回は、これらのメリットについて、具体的に解説したいと思います。
青色申告特別控除
青色申告を選択し、複式簿記により作成した損益計算書や貸借対照表を確定申告書と合わせて提出すると、所得から65万円を差し引いた上で所得税を計算することができます(期限内申告に限ります)。
たとえば、事業による収入が500万円、必要経費が100万円だとすると、
白色申告の場合:500万円-100万円=400万円として税額計算をする
青色申告の場合:500万円-100万円-65万円=335万円 として税額計算をする
このように青色申告の場合は、さらに65万円を差し引いた335万円を基礎として税額計算することができます。
特別控除額の65万円は、節税額そのものではなく、あくまで所得から差し引くものですから、実質的な節税額は、65万円に税率を掛けた金額となります。
所得税の税率は、所得の多寡に応じて変動しますので、たとえば税率が10%であれば、6万5千円の節税効果が見込まれます。
さらに、この特別控除には、住民税や国民健康保険を下げる効果もありますから、トータルで考えると、少なくない経済的メリットを受けられます。
なお、複式簿記によらず簡易な方式で会計処理をする場合、特別控除額も10万円に減額されてしまいますから、その分メリットも小さくなりますので、ご注意ください。
青色専従者給与
個人事業をしている人は、手伝いをしてくれる家族に給与を支払う場合もあるでしょう。
その場合、原則として、支払った給与は事業所得の必要経費とすることはできないのですが、青色申告を選択し、必要な手続きを行なった場合に限り、支払った金額を、「青色専従者給与」として事業所得の必要経費とすることができます。
ただし、いくつか注意点があります。
まずは、青色専従者給与の対象となる家族とは、15歳以上で、「専らその事業に従事する」必要があるという点です。
たとえば他に職業を持っていたり、学生だったりする家族に対し、事業を手伝ってくれた対価を支払ったとしても、青色専従者給与は認められません。
また、支払う金額は、あくまでも「業務の対価」として支払うものですから、必要経費を増やしたいからといって、過大な金額を支払うことはできません。
たとえば、業務内容からして、年間100万円程度に相当する仕事に対し500万円を支払っていたとすると、差額の400万円は過大に支払っているとみなされ、必要経費とは認められないのです。
加えて、家族を扶養に入れ、配偶者控除や扶養控除を受けている人は、専従者給与を支払うことによって、そうした控除がなくなってしまうことも理解しておきましょう。
純損失の繰越控除
年間を通して事業が赤字になった場合、給料など他の所得がある場合には、相殺して所得税を計算することができますが、相殺しきれない赤字がある場合、3年間を限度として、赤字の金額を繰り越すことができます。
この繰越計算も、青色申告を選択しているからこそ使えるものです。
年によって利益や損失が大きく変動するような人は、繰越控除を使うことによって、利益がある年分の所得税を下げることができます。
少額減価償却資産の特例
10万円以上の備品等を事業用として購入した場合、その購入費は、「減価償却」という計算をし、複数年に分割して必要経費にしなくてはなりません。
ですから、実際にはお金の支出があるにもかかわらず、購入した年に必要経費とできる金額は少なくなってしまうというのです。
しかし、青色申告を選択している人であれば、「少額減価償却資産の特例」という制度を使うことにより、購入費の全額をその年の必要経費とすることができます。
ただし、この特例を使えるのは、1個あたり30万円未満であり、年間300万円に達するまでのものに限られます。
貸倒引当金
個人事業の場合、商品やサービスを販売した代金を、すぐに受け取れるとは限りません。「売掛金」として処理し、数ヶ月入金を待つということもあるでしょう。
ここで問題になるのが、取引先の経営悪化リスクです。
最悪の場合、取引先の倒産によって、売上の代金を受け取れなくなる「貸倒れ」が発生する可能性もあります。
こうしたときに使えるテクニックが、貸倒れのリスクに備え、将来生じる可能性のある損失を、「貸倒引当金」という名目で計上し、事前に必要経費とするというものです。
さきほど説明した「少額減価償却資産の特例」と同様、貸倒引当金も、将来必要経費となるものを、前倒しで必要経費とするものであり、トータルで考えると、必要経費として認められる金額はプラスマイナスゼロになります。
しかし、こうした制度をうまく使い、利益の多い年分の必要経費を増やすことによって、少なからず節税効果が期待できます。